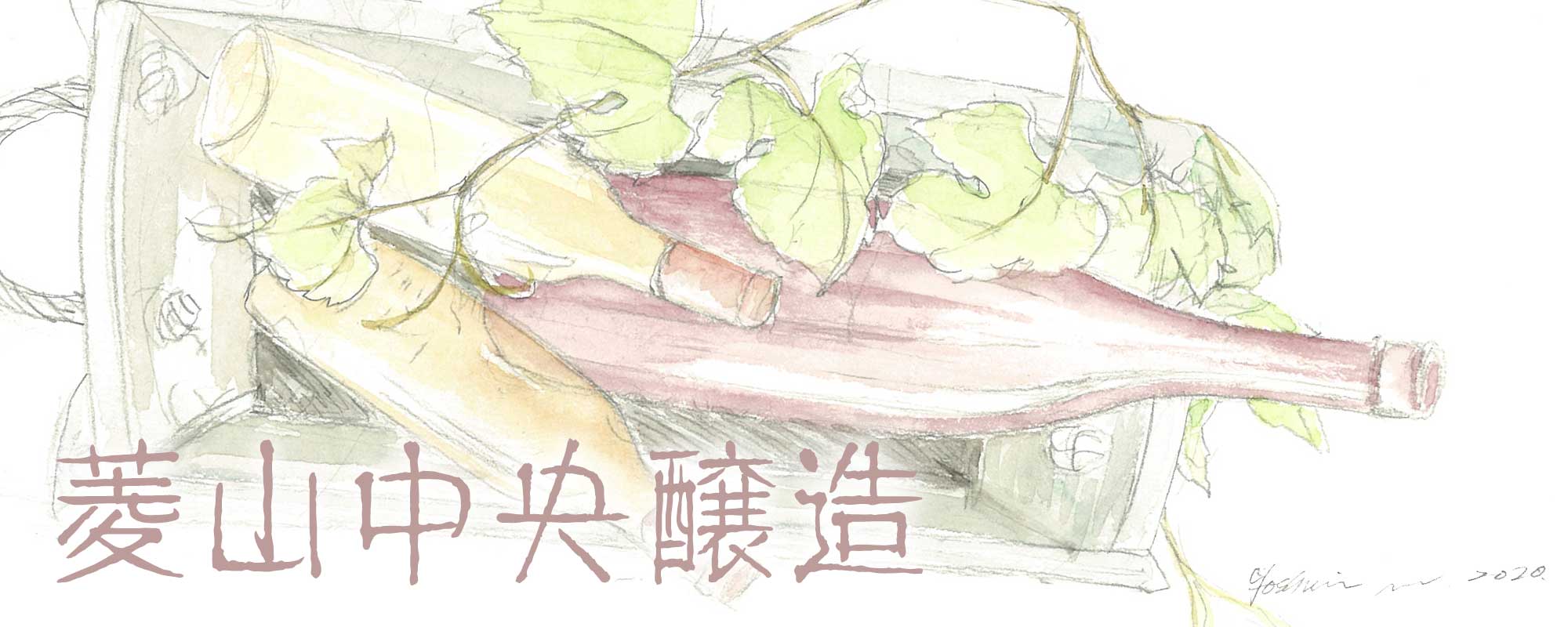
山梨県勝沼にあるぶどう狩り・直売のお店 - ぶどうばたけ
ぶどう狩り、手絞りワイン、ぶどう直販、農業体験、農家民宿の「ぶどうばたけ」
トップページ  菱山中央醸造
菱山中央醸造
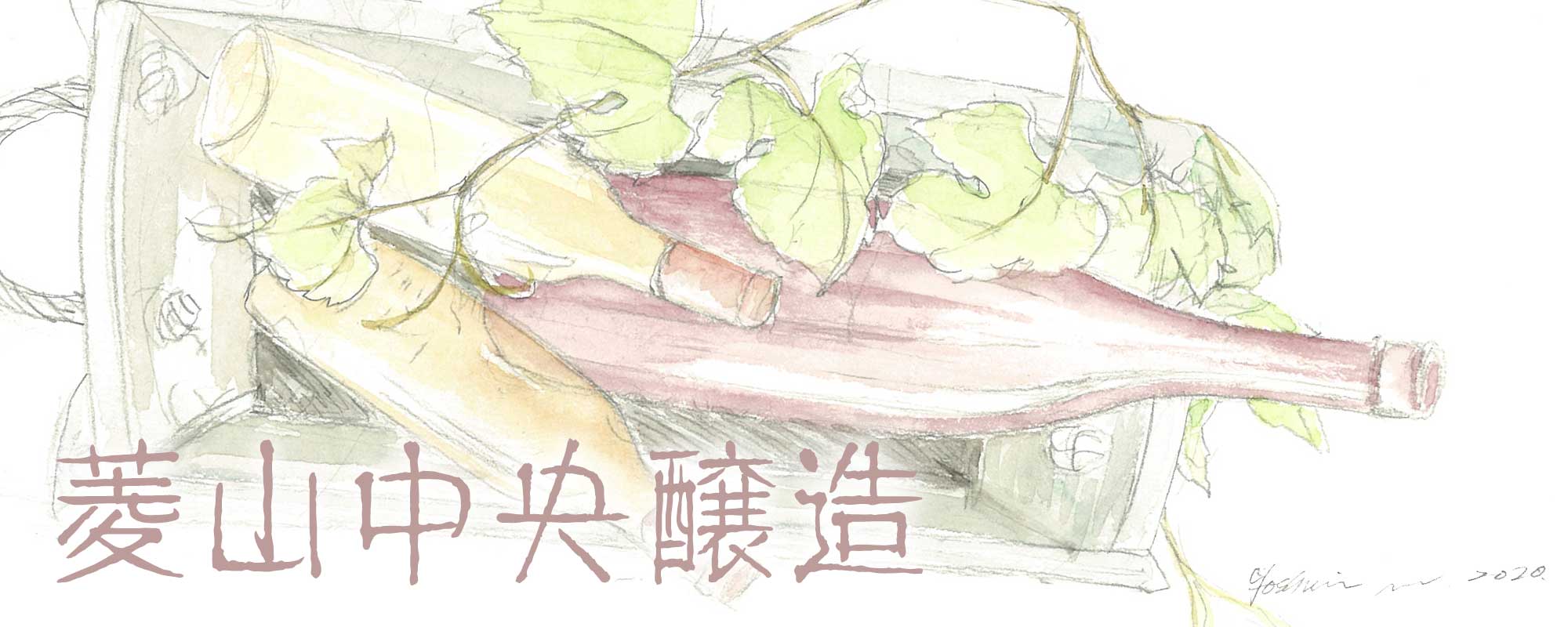
菱山中央醸造有限会社とは
昭和初期に菱山地域に醸造権が下されてから現在に至るまで、地域のぶどう栽培農家の生食用葡萄を原料として自家用消費の為に皆で搾り皆で瓶詰めする葡萄酒蔵である。現在も変わらずこの地域の農家と共に歴史を刻んでいる。
葡萄酒の歴史
勝沼の葡萄酒造りは明治時代、殖産興業の国策から始まりました。
飲料として出荷される一方 農家でも自家用葡萄酒作りが個々で行われました。(密造酒)
太平洋戦争の中ぶどう酒からとれる酒石酸が軍事利用できる為、国から醸造要請が来ますが実用化する前に終戦を迎えます。
昭和初期
ブロックワイン(地域の共同醸造場)
ぶどうの生産農家が多いこの地域独特の仕組みで、農家がぶどうを持ち寄り共同で仕込み酒税を収めたのち農家に分配する仕組み。持ち込む場所が地区割されていたことが由来となっている。当初菱山地区には数か所の仕込み場所があったが戦後2か所に集約され、現在当時からある蔵は菱山中央醸造1軒となった。
持ち帰った農家は晩酌や親戚・知人に振舞ったり冠婚葬祭に欠かせず地酒としてぶどう酒と呼ぶ。
容器
明治時代からガラスの一升瓶が流通し始め 葡萄酒は農家が用意した一升瓶に詰めて農家に配布された毎年管理しビンを再利用している。
当時から、自分が飲む為の葡萄酒なので、仕込みや瓶詰めは農家の方がお手伝いをしていた。
現在でもこの蔵には雇用はなく、三森家と地域役員で管理している。
昭和30年代
菱山地域はデラウエアの一大産地であった。
原料ぶどうは 出荷できない粒が割れてしまったなど商品価値のないいデラウエアであった。
平成8年以降
現在の代表三森斉が家業に入り、10年以上お休みしていた蔵の後継者として活動を始める。
農家は当時全ての葡萄を農協出荷していたが、直売店を農協出荷で初めて試みる。
今まで地元の需要しかなかったが、当時でも珍しい手絞りの蔵であった為、観光客に蔵の見学や試飲をはじめ蔵で一升瓶のワインを販売する。
年農村交流
ワイン好きな方々が徐々に仕込みや瓶詰めに手伝いに来ていただくようになる。一緒に活動し地元に浸透するまでには10年くらいかかる。農村は外部の方の受け入れ態勢が整っていなかった。
ぶどうの品種
昭和50年代から大房の巨峰や甲斐路などぶどうの需要の変化とともに、デラウエアの需要が少なくなり改植。
甲州は生食用として出荷していたが、醸造用ぶどうとしての需要が多くなり、時代と共に甲州ぶどうの葡萄酒に変わる。
醸造家の出会い
池田ワイナリーの池田社長
今までの酒は農家の為のぶどう酒文化であった。
新しい時代新しい甲州の葡萄酒を造るにあたり池田さんとの出会いから、蔵の整備やお酒の管理、醸造についても指導をいただき、この地域の甲州ぶどうの良さを引き出す葡萄酒に変わってきた。
現在も相談は続く。
ロゼワイン試作
完熟した形の悪い葡萄や、畑により色のこない葡萄は出荷してもとても安価で取引される。これらの葡萄を使って新しいワインに挑戦。現在は徐々に量産している。全て生食用の葡萄の棚まとめで造るワインは年によりセパージュも異なる。完熟したぶどうの甘い香りが特徴。
容器
720mlの需要 2000年頃
観光客からの要望と地元農家の家族が少なくなって小瓶に詰めて欲しいなど要望が合わさって、持ち帰りやすい。など少しずつお客様が増えていった。
令和コロナ禍
平成28年秋から三森基史が海外研修から帰り農業と醸造の後継者として地域に入る。
令和になりコロナが流行り始めコロナとの戦いが始まる。
飲食店・会合など集まりの自粛、行動の厳しい規制があり自社でも原料を少なくして対応。
新しい取り組み
コルクの現状
1999年から東京にワインの勉強を始めた頃からコルク問題が始まり、全世界でコルク不足が騒がれ、スクリューキャップの移行や、小瓶の需要も出てきていた。
直売店のお客様から、帰りの電車で飲みたい、扱いやすい瓶がいいなど要望をいただいていた。
180mlの申請とスクリューキャップの需要は一緒でないが、コルク問題は年に1度くらい自社でもコルク不良がある。
今後ますます少人数の生活になり、家族構成が変わるとそれに伴い、1人・2人で飲むタイプの瓶のニーズに変わる。
赤ワインの取り組み
国産100%の赤の葡萄酒を飲みたいという需要は以前からあったが、息子が入り、徐々に管理など任せていくうちにマスカットベリーAの葡萄酒を少しだけ試みる。ロゼワインの後、完熟したマスカットベリーAを醸し、櫂入れを毎日行い丁寧に仕込む。プレスし発酵させる。
小さい蔵だが、地域の農業者の方々と、支えてくれるお客様の時代とニーズを少しずつ取り入れ、古き良き時代の伝統を新しい時代につなげる為、微力ですが農業者という立ち位置で蔵の醸造を地域の方と取り組みたい。
菱山地区の風土
地形
甲府盆地の東に位置する勝沼町の中でも駅の周辺は標高400mから700m近くの南西に向いた斜面に地域があり、扇状地で山裾や丘の地形に棚がありぶどう栽培を行っている。
世界のぶどうの3大条件 水はけ・日当たり・風通し であるがこの地域はすぐ下が岩盤であることや礫が多い為痩せている土地なので、ぶどう栽培には適している。
三森家の所有している畑も傾斜地で機械がはいらず、手作業で草刈りや消毒をおこなう。
1日の寒暖の差が大きく、特に日中の気温の高さと、夜温度が下がるため着色がよくまた、標高が高い為完熟には時間がかかるが、甘味と酸味の整った味の濃い葡萄に仕上がるのが特徴である。
大量生産ができない故高品質の葡萄栽培に変わった地域ならではの条件であると思う。
盆地なので、夏はとても暑く、冬は雪はあまり降らないが、その分底冷えがして、農作業はとても辛く手先が痺れるほど冷たい。人間には厳しい環境である。
水に恵まれなかったので、稲作ができず、貧しい地域で ゆい で助け合ってきた。
この地域は大量生産ができない為、高品質な葡萄を栽培するよう栽培技術を農家は磨いてきた。
地域で後継者を育てる会があったり、100年以上も続く敬老会など、地域の結束は今でも他の地域より堅いと言える。この地域の農業者の集まりだったので、この蔵が現在も続いている所以であると思う。
-
 甲州の畑
甲州の畑
-
 甲州の畑
甲州の畑
葡萄酒の工程
仕込み
10月中下旬の週末3日で行う
-
 完熟した甲州
完熟した甲州
-
 仕込み風景
仕込み風景
計量
農家の原料を全て計量する。原料ぶどうは個々の農家が痛みなどを除去したものを持ち寄る。
-
 持ち寄った甲州
持ち寄った甲州
破砕
破砕機に入れ醸造しやすいように粒をバラバラにする。
-
 破砕
破砕
-
 破砕機
破砕機
-
 破砕後のぶどう
破砕後のぶどう
圧搾・搾汁
木製のバスケットにいれ上から加圧し搾汁する。
-
 ロゼ仕込み
ロゼ仕込み
-
 仕込準備
仕込準備
-
 工程
工程
加圧しても木製の為柔らかく搾れる。除梗しなくても梗は傷まない。
-
 加圧
加圧
発酵・熟成
葡萄酒の味が決まるとても大切な作業 30〜40日かけ ゆっくり発酵する(低温発酵)。
果汁は外気温により発酵の速さが変わるので、毎日管理に注意が必要。
一冬熟成させる。
瓶詰め
濾過したタンクの葡萄酒を全て一升瓶と720ml瓶に詰める。
12月の下旬にほんの少し新酒として、3月のお彼岸の前に瓶詰め作業を終える。
春になり本格的に農作業が忙しくなる前に終了する
-
 一升瓶蔵出し
一升瓶蔵出し
打栓・キャップシール
瓶詰めされた葡萄酒に栓をする。
一升瓶は裏張りを貼り、720mlはキャップシールをコテで温度をかけて行う。
この蔵は農家が飲むために造るので、エチケット(ラベル)は無い。
必要事項や字の大きさも全て国税局で指示されているので蔵から出るときには必ずこの作業が必要。
-
 菱山
菱山
葡萄酒の紹介
甲州白辛口 一升瓶
720mlキャップシール ゴールド
この蔵で最も多く醸造され、地域の農業者に愛されているぶどう酒。
夏は冷やしてキリッと、冬は常温で、その年のぶどうの出来により味わいは異なるが日常の食事に食前から食後まで変わらず食材を邪魔せず味わえます。
完熟した甲州の香りと味わいはぶどうそのもののよさと言えます。
甲州白甘口
720mlキャップシール 白
秋から冬にかけ、最近は特に女性に人気の商品です。
豊かな甲州の甘みを感じつつ、煮物など根菜類の甘さと一緒に味わうのがとても良いと好評。
味噌・醤油は発酵しているので、共鳴して日本食の旨味として最高です。
※ 辛口と甘口の違いは 発酵時間によるもので、決して混ぜたりするわけではありません。
ロゼワイン
720mlキャップシール 赤
11月中旬 直売店で棚に残した食用のぶどう達を全て収穫します。また、地域の一部農家の色や形の悪い完熟したぶどうなど。多いときは10種類を超えるぶどうの品種があり
シャインマスカットも最近は入っています。
完熟したぶどうの芳醇な香りと、マスカットベリーAを醸し色付けした葡萄酒は、春先には桜色、段々と熟成していくと色が濃くなり、クリスマスの頃には濃くなりルビーに近い色に。
瓶熟するのは味わいと色もとてもチャーミング。デザートワインや、単体で楽しむのも素敵です。
赤ワイン
720mlキャップシール 赤 ゴールド
マスカットベリーAのみで現在は仕込みます。
完熟したマスカットベリーAを小さな入れ物に入れ、櫂入れを毎日丁寧に行い、皮から色を種からタンニンを複雑な味わいと色を抽出します。樽などを使っていないので、すっきりと飲みやすい。家庭の炒め料理や簡単なお肉料理にとても合います。熟成していない山羊のチーズなど優しいチーズと共に召し上がってください。
皆様の要望を聞きながら、赤ワインの需要が広がると、耕作放棄地対策など今後農地を広げていこうと思います。
スパークリングワイン
青デラヴァンムスー
有限会社ぶどうばたけ開発 2010年頃 当時からのラベルもあります。
以前デラウエアの産地だった菱山地区は高齢者や栽培難所地域には改植していない古い棚に昔のデラウエアが栽培されており、改植には時間と管理には歩お金がかかるため、現在の葡萄と棚を生かし、最低限の手を入れ葡萄酒原料にして新商品開発を行いました。
菱山中央醸造ではスパークリングワインは作れないので、他社の小さい原料でお願いできるところに依頼しました。
現在に至るまで、結婚式の乾杯やお土産に使われる方々もおられ、ワインの苦手な方にも甘めなので好まれています。
夏の暑いときには冷やしてビールの代わりに、年間イベントには乾杯のお酒として日本人に泡物はマッチします。
新商品紹介
180mlスクリューキャプワイン 4品種
-
 180mlスクリューキャプワイン
180mlスクリューキャプワイン
基本
一升瓶・720mlと同じぶどう酒になります。
瓶のサイズにより発酵が異なるので、同じワインの品種でそれぞれ購入し、飲み比べしていただいてはいかがでしょうか。
特徴
菱山中央醸造の従来の商品とちがい、こちらの商品にはラベルがあります。お客様に販売することを目的にした商品です。
瓶が小さいので、飲み切りや、飲み比べなど、家飲み用として、1人で少し味わいたい時に最適。
小瓶なので色々と使いかってが良い商品になっています。
スクリューキャップ:従来のワインはコルク形式なので、抜栓や保存も厳密に言うと気にすることも多いのが難点でした。スクリューキャップにすることにより、旅先で何もない時、気軽に飲めて飲み残しも簡単。力のない女性に扱いやすいのが利点です。
山梨の思い出や、贈答用、まずはお試しサイズから。ホテルなどの冷蔵庫に入れても簡単!
素敵なシーンを一緒に過ごしていただきたい。
昭和初期からのぶどう酒蔵のお酒は希少で出回りません。
気に入ったら、是非720mlや中には一升瓶もいかがでしょうか?